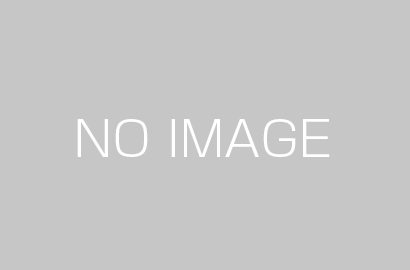皆さんは、《アーティチョーク》と言う言葉を聞いた事ありますか??
私自身、あまり見たことも聞いたこともないのですが、テレビで紹介していたので、紹介して行こうと思います。
アーティチョークとは?
日本では、あまり馴染みがありませんが、ヨーロッパや、アメリカのマーケットでは、ポピュラーな野菜です。
つぼみを茹でて、少し肉厚になった萼やつぼみの芯を食べます。
萼をすべてひっぺがえした芯の部分「アーティチョーク・ハート」は軟らかくてたっぷり食べ応えがあります。デンプン質でほくほくしており、味は、ソラマメとクリを合わせような風味があります。古くから野菜として親しまれ、改良された品種もたくさんあります。日本では江戸時代中期に栽培されていた記録がありますが、広まらなかったようです。
野菜なのですが、とてもきれいなお花が咲きます。
お花は、地中海沿岸原産の毎年花を咲かせる多年草といわれています。
大形の草花で丈は2mを超すこともあります。主な開花期は初夏~夏で、アザミに似た紅紫色の花を咲かせます。葉っぱは深いぎざぎざが入り、茎は極太で、根っこはごついです。全体的にアザミに似た姿ですが、トゲはありません。冬前になると寒さに備えて地面に葉をべちゃっと広げたロゼット状になり、春に暖かくなると茎を立ち上がらせます。
ウロコのような萼が重なった若いつぼみが食用となります。つぼみと言っても大きさはソフトボール大で、萼もギターピックのようです。
和名はチョウセンアザミですが、原産地は地中海沿岸で日本に入ってきたのもオランダ経由と言われており、由来はよくわからないそうです。
不思議なお花ですよね。
アーティチョークの食べ方
食べ方として、一般的には茹でて食べます。
そのためにまず、固く閉じたガクの部分を先っぽをカットします。
これはトゲだらけで危ないからだそうです。
しかも同時に火の通りを良くできると言うメリットがあります。
とてもアクの強い野菜なので、作業は手早くします。 終わったら変色しないように、すぐにレモン水や、酢水に浸します。
30分ほど茹でますが、大して柔らかくなっているようでもないですが、これで出来上がりです。
萼を外側から一枚剥がして、先程カットした方を手で持ち、
半分から付け根の部分を歯で削り取るようにして食べます。
そして何枚あるかわからない萼を、一枚一枚剥がしていくと、今度は白いけむくじゃらの物体が現れます。
これは花びらになる部分で、この時は真っ白ですが、 咲く時には美しい薄紫色になるんです。
がしかし…、これはアーティチョークの食べられない部分ですので、丁寧に取り除きましょう。
最後に残った部分が、アーティチョークハートと言われるご馳走だそうです。
アーティチョークの味とは?!
食べた事がない方は、どんな味なのか気になってきたんじゃないでしょうか?
見た目が野菜というよりは植物という感じだし、
つぼみを剥いて食べるなんてワイルドな食材はそうありませんよね。
味はサツマイモという方もいらっしゃいますが、そら豆みたいだと言う方もいらっしゃいます。
また、なんとなく栗に似ているという方もいます。
この3つの持つ、ホクホクとした食感と濃厚な味わいがアーティチョークに通じる面があるからでしょう。
ただイモやマメと違うのは、ほんの少しえぐみがあるという事です。
そのため、ユリ根みたいだと言う方もいます。
アーティチョークの効果効能
アーティチョークは、肝臓にとてもいいそうです。
肝臓の回復を早め、重要な臓器の再生をたすけてくれます。
弱った細胞を再生するだけでなく、胆汁の生成も促進してくれます。肝炎、肝硬変、または肝機能不良のような疾患を治療するのに優れています。
煎じて飲むとアーティチョークの全ての効力を得られるため、とても効果的ですよ。
作り方はまず、アーティチョークを一つ、柔らかくなるまで沸騰したお湯で茹でます。レモン半分の果汁を加え、食後に飲んでください。
アーティチョークは、脂肪燃焼を助ける効果に優れています。その利尿作用および浄化作用が、体から有害物質の排除を助けてくれます。
飲むときは是非、煎じたものを飲んでくださいね。
まとめ
不思議な花のような、野菜のような、不思議な食べ物。アーティチョーク。
いかがでしょうか??
食べたり飲んだり、工夫次第でいろんな食べ方があります。
あなたも是非、ぴったりの食べ方を見つけて、食べて見てくださいね。